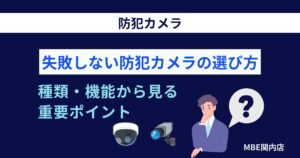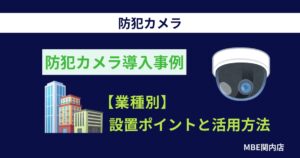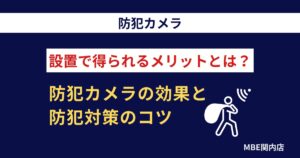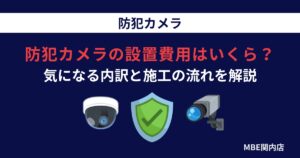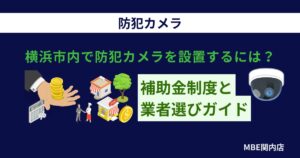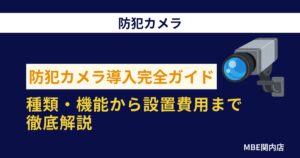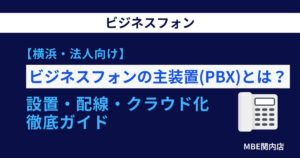【2025年最新版】コピー機で特殊素材印刷|厚紙・光沢紙・シール・封筒・和紙の設定方法

オフィスのコピー機は、普通紙での印刷が基本ですが、実際の業務では厚紙や光沢紙、シール用紙など様々な特殊素材への印刷が必要になることも多いでしょう。しかし、「この素材はコピー機で印刷できるのか?」「設定はどうすればいいのか?」といった疑問を抱えている方も少なくありません。
本記事では、コピー機で印刷可能な特殊素材の種類から、適切な設定方法、注意すべきポイントまで、オフィスワークに役立つ実践的な情報を詳しく解説します。コピー機の機能を最大限活用し、業務効率の向上につなげていきましょう。
💡 コピー機の導入・メンテナンスでお困りではありませんか?
MBE関内店では、中古コピー機の販売から設置、メンテナンスまで一貫してサポートいたします。特殊素材印刷についてもお気軽にご相談ください。
今すぐ相談したい方はこちら
\ 無料見積もりはこちら /
コピー機で厚紙や光沢紙は使える?印刷設定と注意点を徹底解説
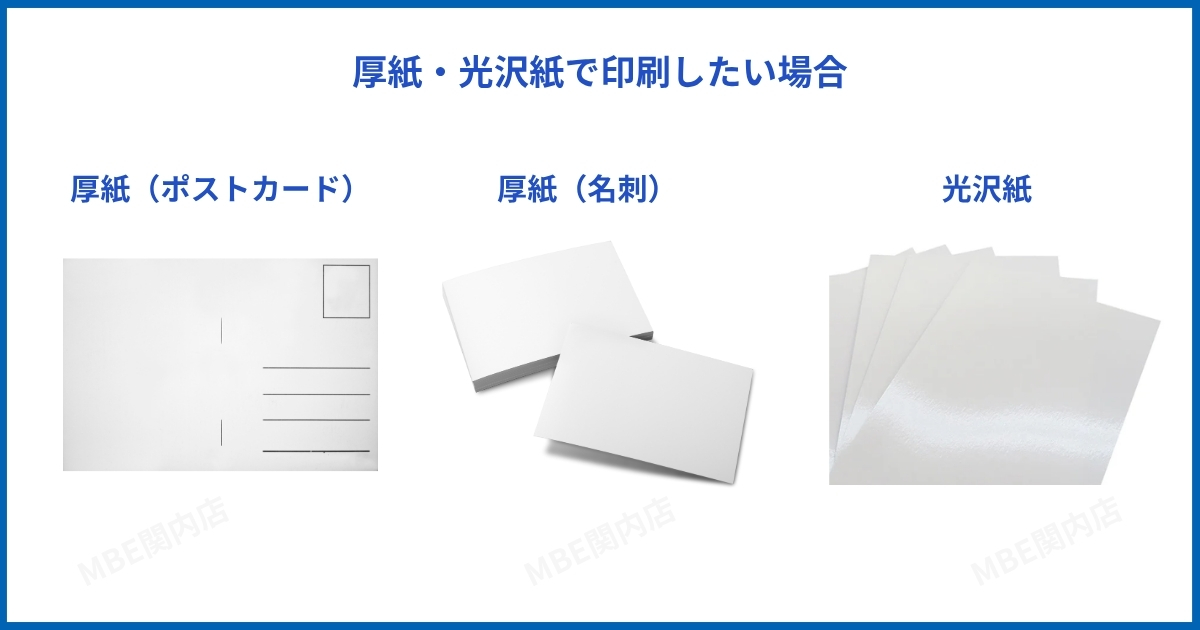
コピー機での厚紙・光沢紙印刷は、適切な設定と注意点を守れば十分に可能です。まず、対応可能な厚紙の目安として、一般的なオフィス用コピー機では90g/㎡から200g/㎡程度(普通紙の約2〜4倍の厚さ)までの用紙に対応しています。これは名刺用紙やポストカード、プレゼンテーション資料用の厚手用紙に相当します。
光沢紙については、インクジェット用とレーザープリンター用で大きく異なります。レーザープリンター対応の光沢紙を必ず選択することが重要で、インクジェット用光沢紙を使用すると、トナー(粉状のインク)が定着せずに剥がれたり、機器内部を汚損したりする可能性があります。
厚紙・光沢紙印刷の基本設定
厚紙や光沢紙を印刷する際の基本設定手順は以下の通りです:
1. 用紙設定の変更
プリンタードライバーまたはコピー機本体のメニューから「用紙の種類」を変更します。厚紙の場合は「厚紙1」「厚紙2」「カードストック」などの項目を、光沢紙の場合は「光沢紙」「コート紙」などを選択しましょう。
2. 印刷温度の調整
厚紙や光沢紙は普通紙よりも熱の伝わり方が異なるため、印刷時の加熱温度を適切に調整する必要があります。多くの機種では用紙の種類を設定することで自動的に調整されますが、手動設定が可能な場合は、厚紙では温度を上げ、光沢紙では適度に抑えることがポイントです。
3. 印刷速度の調整
特殊素材の印刷では、品質を重視するため印刷速度を落とすことが推奨されます。「高品質モード」や「写真モード」を選択することで、自動的に適切な速度に調整されることが多いです。
トラブル防止のための注意点
厚紙・光沢紙印刷でよく発生するトラブルとその対策について説明します。最も多いのが紙詰まりです。厚紙の場合、用紙ガイドの調整が不十分だったり、一度に大量の用紙をセットしたりすることが原因となります。光沢紙では、湿気による反りや、静電気による用紙同士の張り付きが問題となることがあります。
また、印刷後のインクの剥がれも注意すべき点です。特に光沢紙では、表面が滑らかなため印刷したインクが紙にしっかりと付着しにくく、印刷後に指で触ると汚れる場合があります。この場合は、印刷温度を上げるか、印刷後十分に冷却時間を取ることで改善されます。
さらに、厚紙印刷では排紙トレイでの用紙の反りにも注意が必要です。印刷直後は熱で用紙が反りやすいため、印刷枚数を調整し、こまめに排紙トレイから取り出すことが大切です。
コピー機でシール・ラベル用紙を印刷する方法【詰まりやすい時の対処も紹介】

シール・ラベル用紙の印刷は、オフィスでの商品ラベル作成や郵送作業において重要な業務の一つです。しかし、シール用紙は通常の用紙と構造が大きく異なるため、適切な取り扱いが必要となります。
シール用紙は表面の印刷面、粘着層、台紙(剥離紙:シールを剥がすときに残る裏紙)の3層構造になっています。この構造により、通常の用紙よりも厚みがあり、また粘着層があることで機器内での搬送に特別な注意が必要です。
シール用紙選択のポイント
コピー機でシール用紙を使用する際は、レーザープリンター対応のシール用紙を必ず選択してください。インクジェット用シール用紙を使用すると、粘着剤が熱で溶け出し、機器内部に付着して故障の原因となります。
また、シール用紙の品質も重要な要素です。安価な製品では粘着層が薄く、印刷時の熱で台紙から剥がれやすくなったり、逆に粘着が強すぎて給紙時に問題を起こしたりする場合があります。業務用途では信頼性の高いメーカー品を選択することをお勧めします。
印刷設定と注意事項
シール用紙印刷時の設定では、用紙の種類を「ラベル用紙」または「特殊紙」に設定します。多くのコピー機では専用のラベル用紙設定が用意されており、これにより定着温度や搬送速度が自動調整されます。
印刷方向にも注意が必要です。シール用紙には繊維方向があり、この方向に対して適切に印刷することで紙詰まりのリスクを軽減できます。一般的に、長辺方向から給紙する方が安定した印刷が可能です。
印刷枚数については、連続印刷よりも小ロットでの印刷を推奨します。シール用紙は熱がこもりやすく、大量の連続印刷では粘着剤の劣化や紙詰まりのリスクが高まります。
詰まりやすい時の対処法
シール用紙で紙詰まりが頻発する場合の対処法をご紹介します。まず確認すべきは用紙の保管状態です。シール用紙は湿気に敏感で、高湿度環境では反りや波うちが生じやすくなります。使用前に室温で平らな場所に1時間程度置き、用紙を安定させることが効果的です。
給紙トレイの調整も重要なポイントです。用紙ガイドは用紙にぴったりと合わせ、きつすぎず緩すぎない状態に調整します。また、一度にセットする枚数は通常用紙の半分程度に抑えることで、給紙不良を防げます。
それでも詰まりが解決しない場合は、機器内部の清掃が必要な可能性があります。粘着剤の付着により用紙送りローラー(用紙を機械内部に送り込む部品)の性能が低下している場合があるため、専門業者による定期メンテナンスを検討することをお勧めします。
コピー機のトラブル・メンテナンスはお任せください
紙詰まりや印刷不良でお困りの際は、30年の実績を持つMBE関内店にご相談ください。自社エンジニアによる迅速な対応で、業務停止時間を最小限に抑えます。
🏢 コピー機のトラブルでお困りの企業様へ
神奈川・東京エリアで毎年500件超の設置実績!専門技術者が迅速対応
緊急対応もお任せください
\ メンテナンス依頼・無料診断/
コピー機で封筒・はがき・名刺を印刷するコツ【サイズ設定と用紙トレイの使い分け】

封筒、はがき、名刺の印刷は、オフィスでの日常的な業務において頻繁に行われる作業です。これらの用紙は通常のA4用紙とは大きくサイズや厚みが異なるため、適切な設定と取り扱いが印刷品質と作業効率に大きく影響します。
封筒印刷の基本設定とコツ
封筒印刷では、まず封筒の種類とサイズの正確な把握が重要です。一般的なビジネス用途では長形3号(120×235mm)、長形4号(90×205mm)、角形2号(240×332mm)などが使用されます。コピー機の設定では、これらの標準サイズが登録されていることが多いため、適切なサイズを選択しましょう。
封筒の給紙方向は特に注意が必要です。封筒の開口部を下または右側に向けてセットすることが一般的で、これにより印刷時の熱で封筒が閉じてしまうトラブルを防げます。また、封筒は通常の用紙よりも厚いため、手差しトレイまたは多目的トレイを使用することが推奨されます。
印刷設定では、用紙の種類を「封筒」に設定し、厚みに応じて「厚紙」モードを併用することで品質の向上が期待できます。また、印刷余白の設定にも注意が必要で、封筒の糊付け部分を避けた印刷領域を設定することが重要です。
はがき印刷の効率的な方法
はがき印刷では、用紙サイズを「はがき(100×148mm)に正確に設定することから始まります。年賀状や暑中見舞いなどの季節的な大量印刷では、事前のテスト印刷が重要で、1枚目でレイアウトや色調を確認してから本格的な印刷を行いましょう。
はがきの場合、表面と裏面で紙質が異なることがあります。印刷面(通信面)は滑らかで、宛名面はざらつきがあることが一般的です。このため、写真やカラー印刷では通信面を、文字中心の印刷では宛名面を使用するなど、用途に応じた使い分けが効果的です。
連続印刷時は、はがきの反りに注意が必要です。印刷後の熱でカールが発生しやすいため、印刷後は平らな場所で重しを載せて冷却することで、きれいな仕上がりを保てます。
名刺印刷の品質向上テクニック
名刺印刷では、用紙選択が最も重要な要素となります。一般的な名刺用紙の厚さは180g/㎡から220g/㎡程度で、コシがあり高級感のある仕上がりが求められます。用紙の表面処理(マット、光沢、エンボスなど)によっても印刷方法が変わるため、使用する用紙に適した設定を選択しましょう。
名刺のレイアウト設計では、裁断を考慮した余白設定が重要です。通常、名刺サイズは91×55mmですが、印刷時は若干大きめに印刷し、後で裁断することで美しい仕上がりが得られます。また、文字やロゴが裁断線に近すぎると、裁断のずれで切れてしまう可能性があるため、重要な要素は中央寄りに配置することが大切です。
品質の向上には、高解像度での印刷設定が効果的です。名刺は手に取って見られることが多いため、文字の鮮明さや画像の美しさが重要になります。「高品質」または「写真」モードを選択し、やや印刷速度を落としてでも品質を優先することをお勧めします。
コピー機でマグネットシートや布への印刷は可能?対応機種と注意点

マグネットシートや布への印刷は、従来の用紙印刷とは大きく異なる特殊な印刷領域です。これらの素材への印刷可能性は、使用するコピー機の種類と仕様に大きく依存します。
マグネットシート印刷の可能性と制限
マグネットシートへの印刷について、まず理解すべきは一般的なオフィス用レーザーコピー機では印刷が困難であるということです。マグネットシートは通常の用紙よりもはるかに厚く(通常0.4mm〜0.8mm)、また素材の性質上、高温での定着処理に適していません。
しかし、専用のマグネットシート用紙を使用することで、一部のコピー機での印刷が可能となります。これらは表面に印刷可能なコーティングが施されており、レーザープリンター対応として設計されています。ただし、使用前にお使いのコピー機が対応しているかメーカーに確認することが重要です。
マグネットシート印刷では、手差しトレイの使用が必須となります。自動給紙では厚みによる搬送トラブルが発生するリスクが高いためです。また、印刷後は十分な冷却時間を設けることで、磁性による機器への影響を最小限に抑えることができます。
布への印刷技術と対応機種
布への直接印刷は、インクジェット方式の大型プリンターや専用の布印刷機で行われることが一般的で、通常のオフィス用レーザーコピー機では困難です。レーザー方式では、トナーの定着に高温処理が必要となり、多くの布素材では変色や収縮が発生してしまいます。
ただし、転写シートを利用した間接的な布印刷は可能です。専用の転写シートにレーザーコピー機で印刷し、その後アイロンなどで布に転写する方法です。この方法では、Tシャツやトートバッグなどへのオリジナルデザイン印刷が実現できます。
近年では、紫外線で固めるタイプの特殊インクを使用するUVプリンターの普及により、布を含む様々な素材への直接印刷が可能となっています。これらの機器では、綿、ポリエステル、キャンバス地など、多種多様な布素材に高品質な印刷が可能です。
特殊素材印刷時の機器への影響と対策
マグネットシートや布などの特殊素材を印刷に使用する際は、機器への影響を十分に考慮する必要があります。まず、給紙ローラーや搬送ベルトへの負荷が通常よりも大きくなるため、使用頻度を抑え、定期的なメンテナンスを行うことが重要です。
また、特殊素材からの微細な繊維や粒子が機器内部に蓄積する可能性があります。これにより、印刷品質の低下や機械的な不具合が発生することがあるため、特殊素材使用後は機器内部の清掃を行うことを推奨します。
さらに、保証の観点からも注意が必要です。多くのコピー機メーカーでは、推奨用紙以外の使用による故障は保証対象外となることがあります。特殊素材を使用する前に、メーカーのサポートに確認することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
コピー機で和紙を印刷するには?にじまない設定と用紙選びのポイント

和紙への印刷は、伝統的な文書作成や特別な用途において重要な技術です。しかし、和紙の特性を理解せずに印刷を行うと、インクのにじみや用紙の損傷などの問題が発生する可能性があります。
和紙の特性と印刷への影響
和紙は洋紙とは大きく異なる特性を持っています。繊維が長く、表面に微細な凹凸があることが特徴で、これにより独特の風合いと質感を生み出しています。しかし、印刷の観点では、この特性が課題となることがあります。
和紙の吸水性は洋紙よりも高く、インクやトナーが紙の繊維に浸透しやすい特性があります。これは文字や画像のにじみの原因となり、特に細かな文字や線画の印刷では注意が必要です。また、和紙の厚みや密度にばらつきがあることも、印刷時の搬送や定着に影響を与える要因となります。
にじまない印刷設定のコツ
和紙印刷でにじみを防ぐための最も重要な設定は、印刷濃度の調整です。通常よりもトナー濃度を下げることで、過度なトナー付着を防ぎ、にじみのリスクを軽減できます。多くのコピー機では「薄め」や「-1〜-2」程度の設定が効果的です。
定着温度の調整も重要なポイントです。和紙は熱に敏感で、高温では変色や収縮が発生する可能性があります。可能であれば定着温度を通常よりも低めに設定し、その分定着時間を長めに取ることで、品質の向上が期待できます。
さらに、印刷の細かさ設定の最適化も効果的です。あまりに細かな設定にすると、微細なドットが和紙の繊維に埋もれてしまい、かえって印刷品質が低下することがあります。600dpi程度(通常の印刷よりやや細かめ)の設定で、まずテスト印刷を行うことをお勧めします。
和紙選びの重要なポイント
コピー機での印刷に適した和紙選びは、成功の鍵となります。印刷用途には、表面が比較的平滑で密度の高い和紙を選択することが重要です。楮(こうぞ:桑の木の仲間)や三椏(みつまた:ジンチョウゲ科の植物)を原料とした和紙は、一般的に印刷適性が高いとされています。
厚みについては、薄すぎると原稿送り時に破れるリスクがあり、厚すぎると給紙不良の原因となります。コピー機での使用には、70g/㎡から120g/㎡程度(普通紙と同程度〜やや厚め)の厚みが適しています。また、あらかじめ湿度調整された和紙を選ぶことで、印刷時の反りや波うちを防ぐことができます。
表面処理についても考慮が必要です。ドーサ引き(表面に薄いコーティングを施す伝統的な処理方法)が施された和紙は、インクの浸透を適度に抑制し、にじみの防止に効果的です。ただし、過度なコーティングは和紙本来の風合いを損なう可能性があるため、用途に応じた選択が重要です。
印刷後の取り扱いと保管
和紙への印刷後は、適切な取り扱いと保管が品質維持に重要です。印刷直後は用紙が熱を持っているため、急激な温度変化を避け、平らな場所で自然冷却することが大切です。
乾燥についても注意が必要です。和紙は湿度変化に敏感で、急激な乾燥では反りや亀裂が発生する可能性があります。印刷後は湿度50〜60%程度の環境で、1日程度寝かせることで、安定した状態に戻すことができます。
長期保管では、直射日光を避け、温度・湿度が安定した場所を選択しましょう。また、和紙は酸性環境に弱いため、中性紙のフォルダーや保存箱での保管が推奨されます。
まとめ
コピー機での特殊素材印刷は、適切な知識と設定により、多様な業務ニーズに対応することが可能です。本記事でご紹介した各素材の特性と印刷方法を参考に、オフィスでの印刷業務の幅を広げていただければと思います。
重要なポイントの再確認:
厚紙・光沢紙印刷では、レーザープリンター対応用紙の選択と適切な温度・速度設定が成功の鍵となります。シール・ラベル用紙では、品質の高い専用用紙を使用し、小ロット印刷を心がけることで、トラブルを最小限に抑えることができます。
封筒・はがき・名刺の印刷では、各用紙の特性を理解し、適切なトレイの使い分けとサイズ設定を行うことが重要です。マグネットシートや布への印刷は制限が多いものの、専用材料や転写技術を活用することで実現可能です。
和紙印刷では、にじみ防止のための濃度調整と、和紙の特性に配慮した温度設定が品質向上の要となります。どの素材においても、事前のテスト印刷を行い、最適な設定を見つけることが大切です。
特殊素材の印刷を行う際は、機器への負荷や保証の観点も考慮し、定期的なメンテナンスと適切な使用頻度を心がけましょう。これらの知識を活用することで、オフィスでの印刷業務がより効率的で高品質なものとなるはずです。
印刷に関するより詳細な情報や、機器の選定・メンテナンスについてのご相談は、専門業者にお問い合わせいただくことをお勧めします。適切なサポートを受けることで、長期的に安定した印刷環境を維持することができます。
コピー機選びから特殊印刷まで、MBE関内店がトータルサポート
神奈川・東京エリアで500件超の実績!中古コピー機の販売から設置工事、定期メンテナンスまで自社対応。特殊素材印刷のご相談もお気軽にどうぞ。
今すぐ相談したい方はこちら
\ 無料見積もりはこちら /
横浜のMBE関内店が選ばれる理由
\ 神奈川・東京エリアで30年の実績/
中古品でも高品質、厳選した商品のみ販売しています。自社メンテナンス体制で迅速なアフターサポート。設置工事から保守まで一貫対応